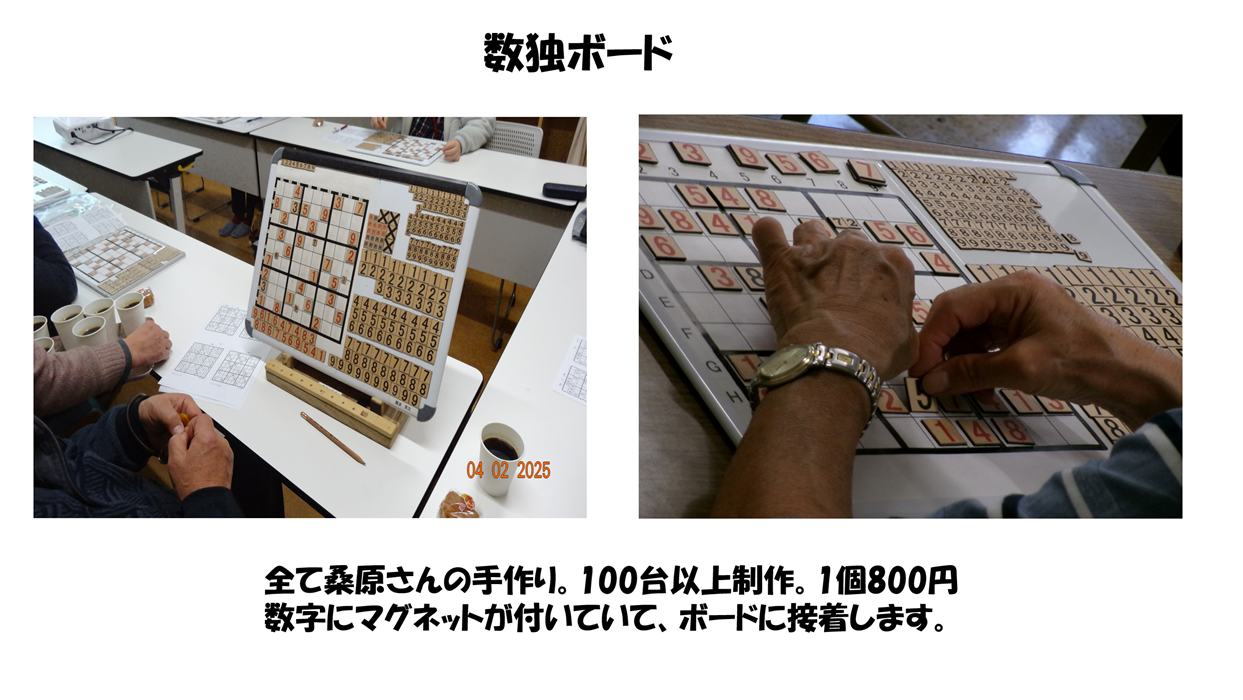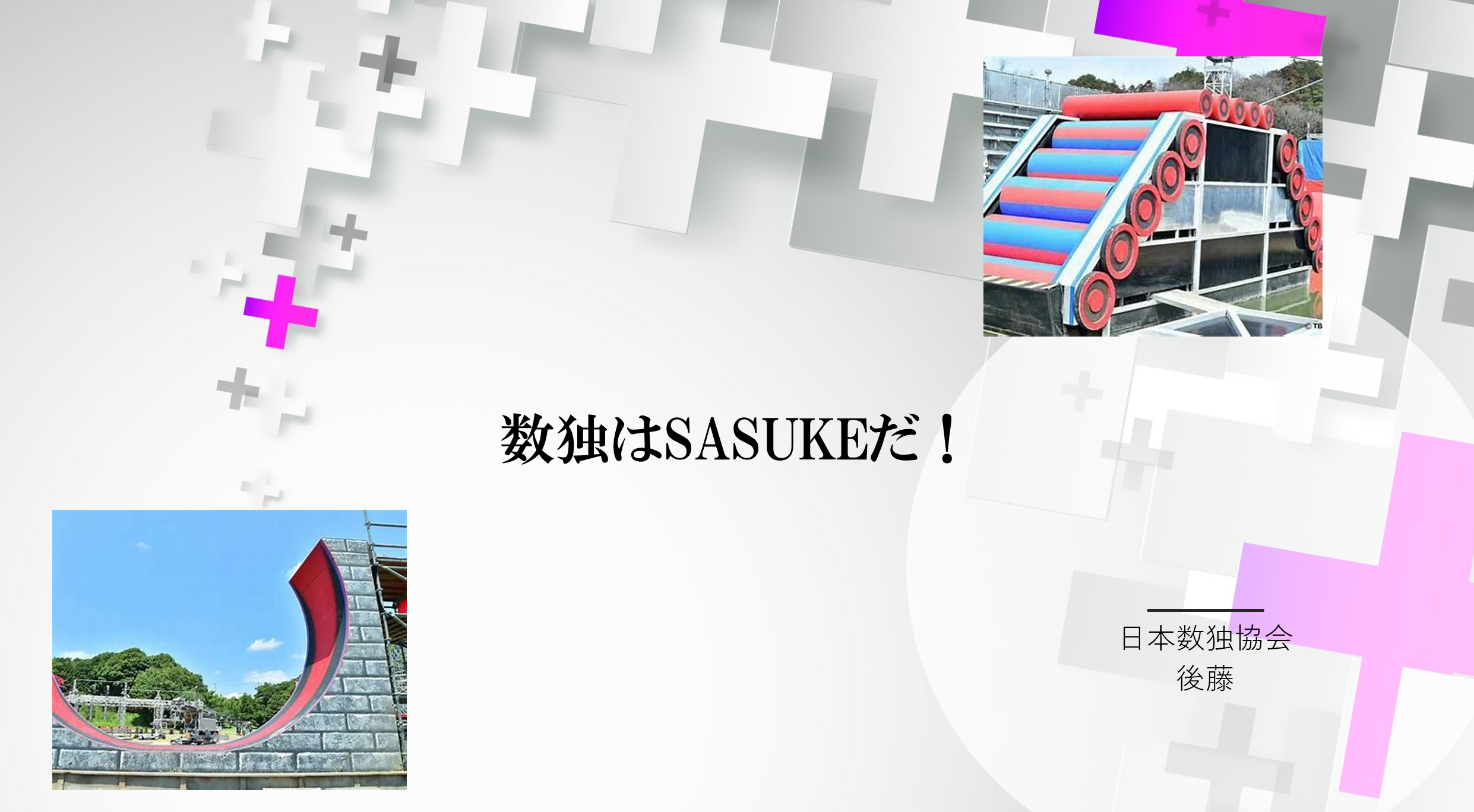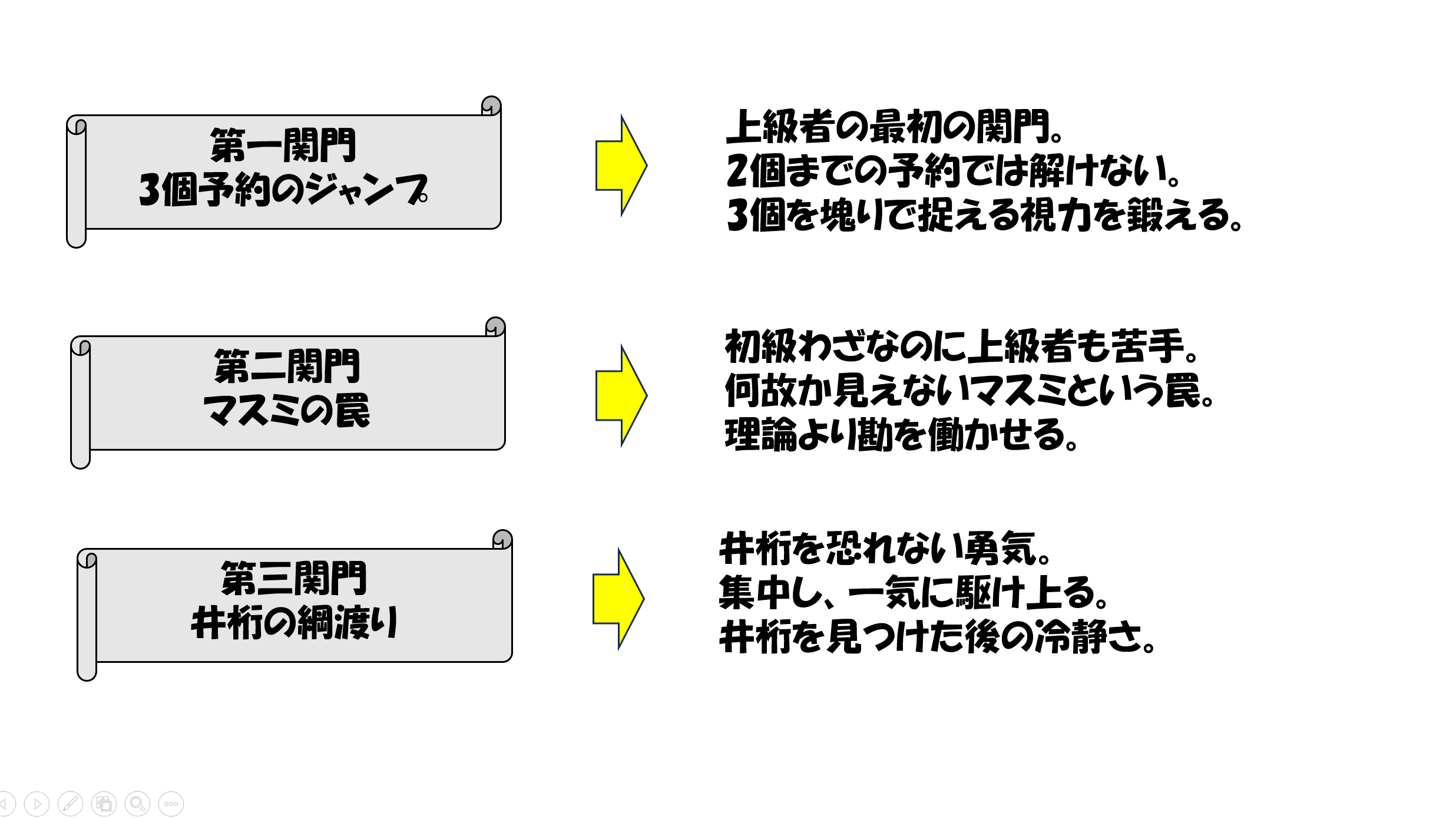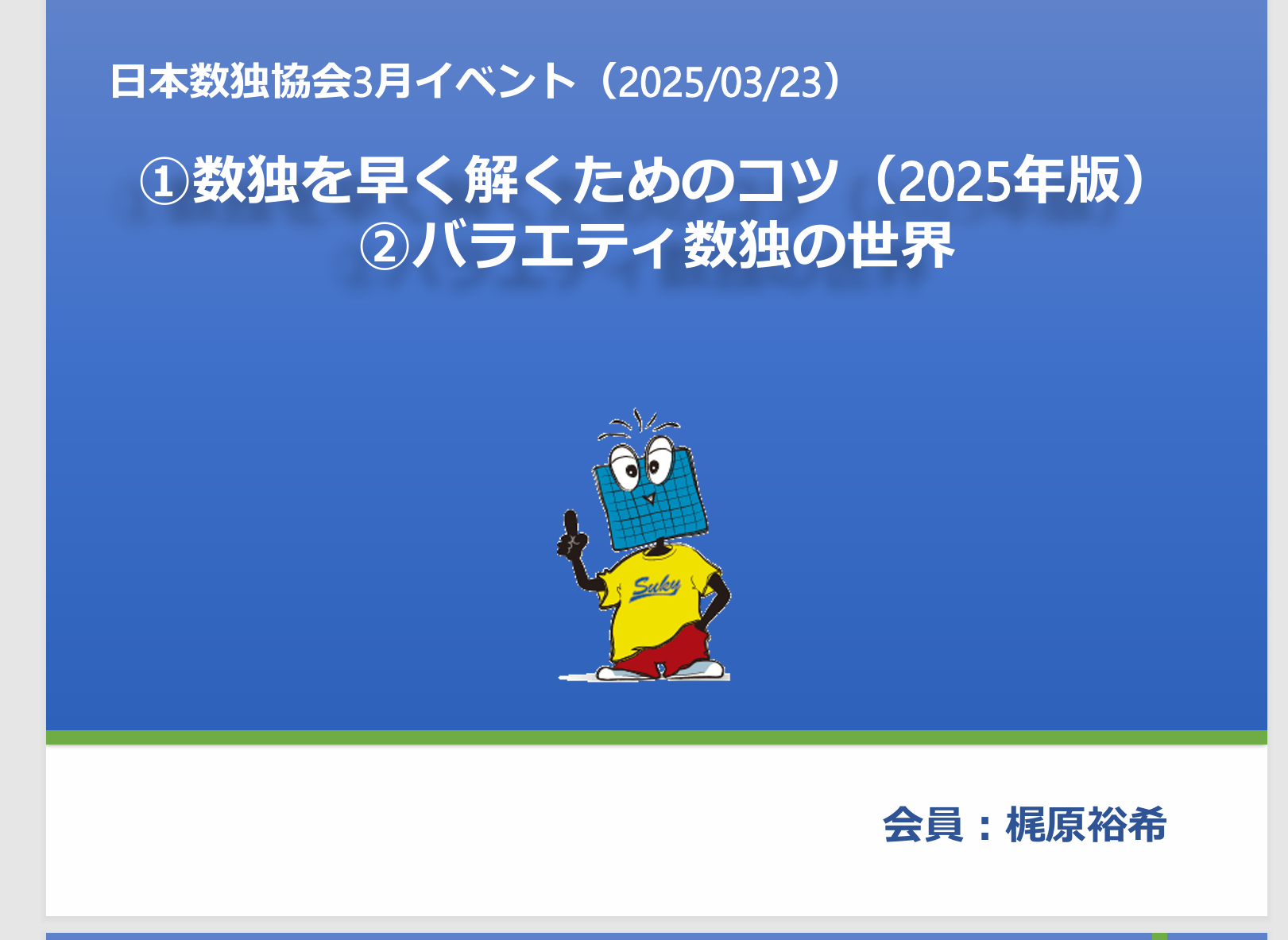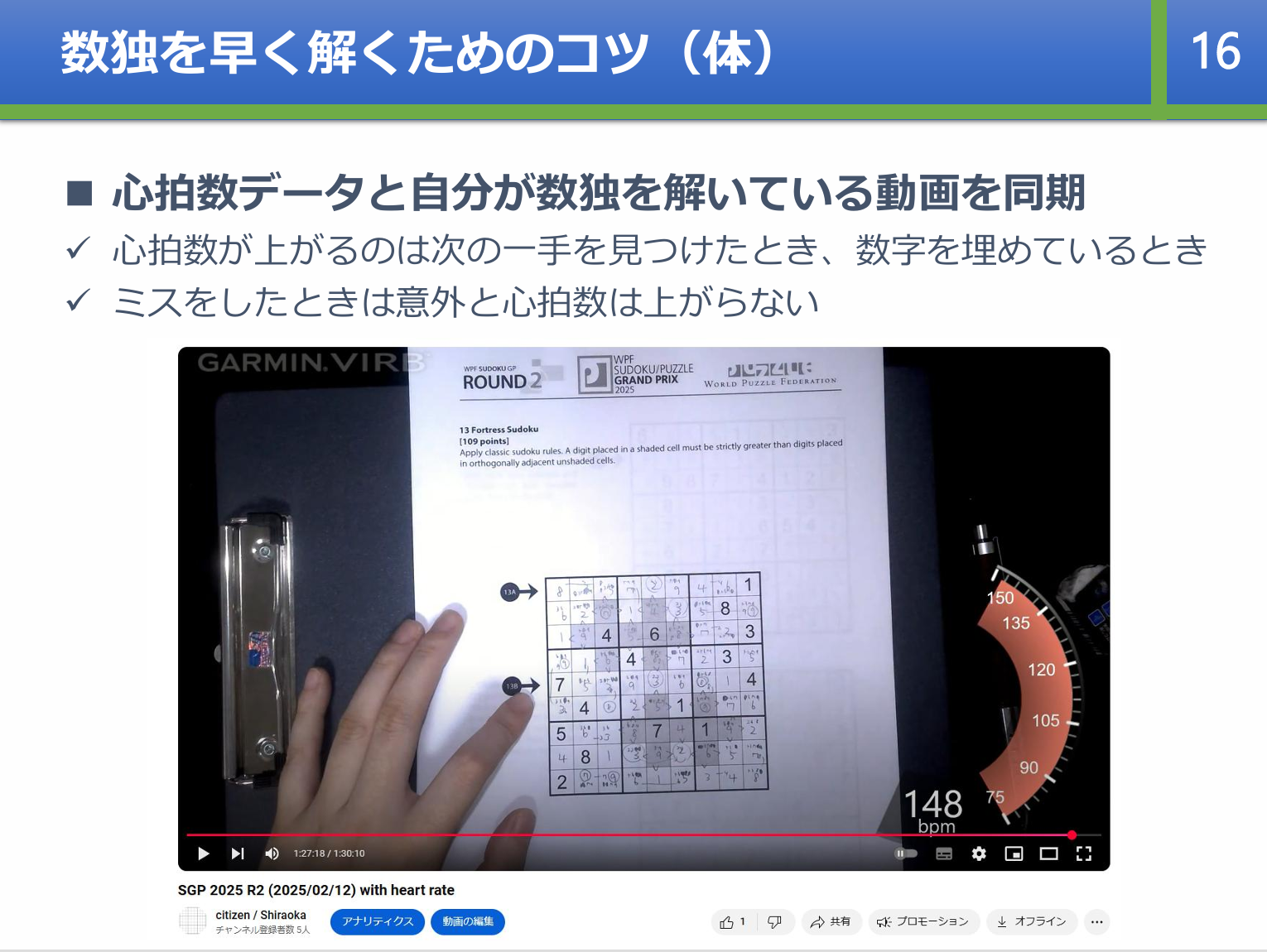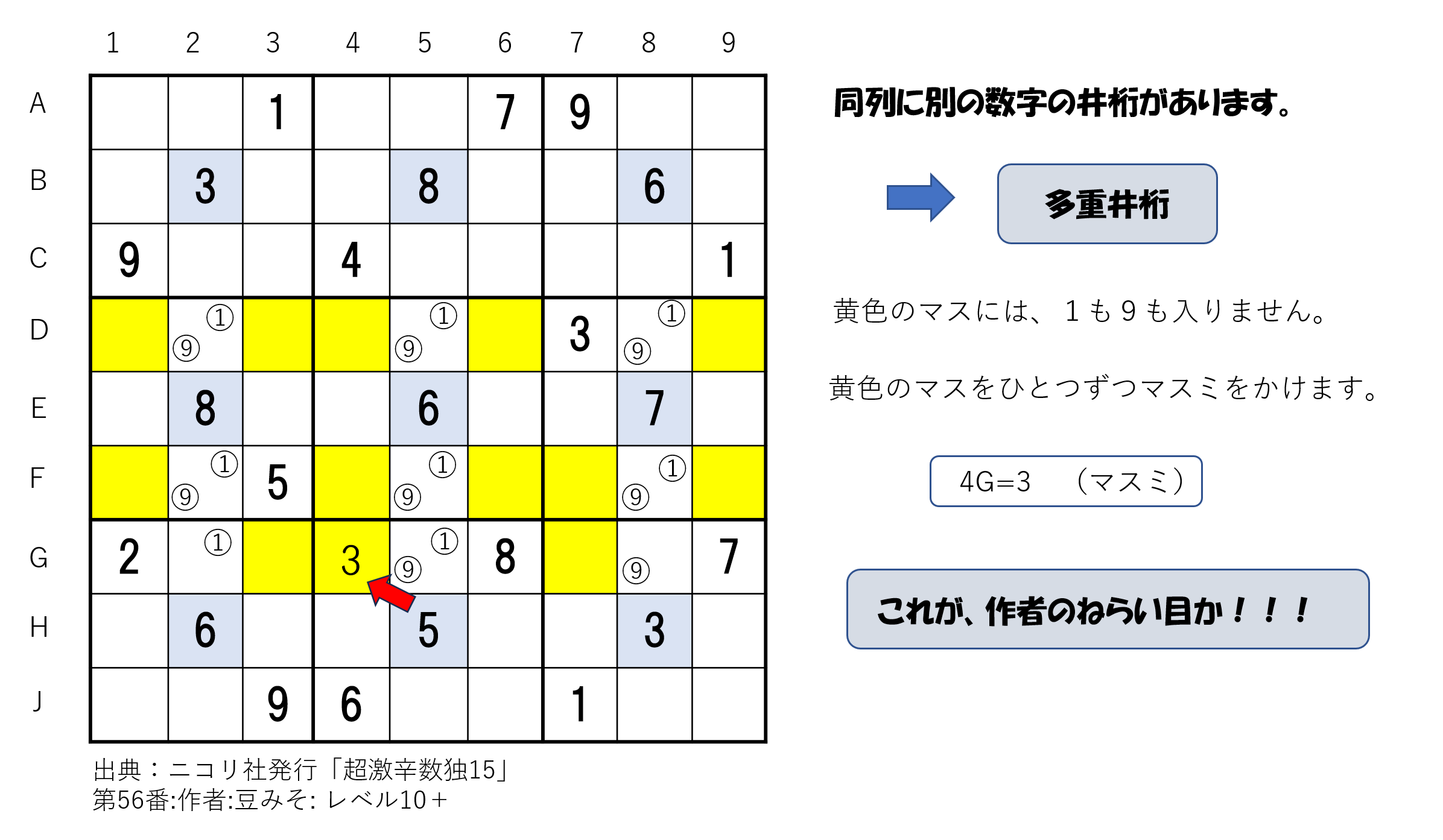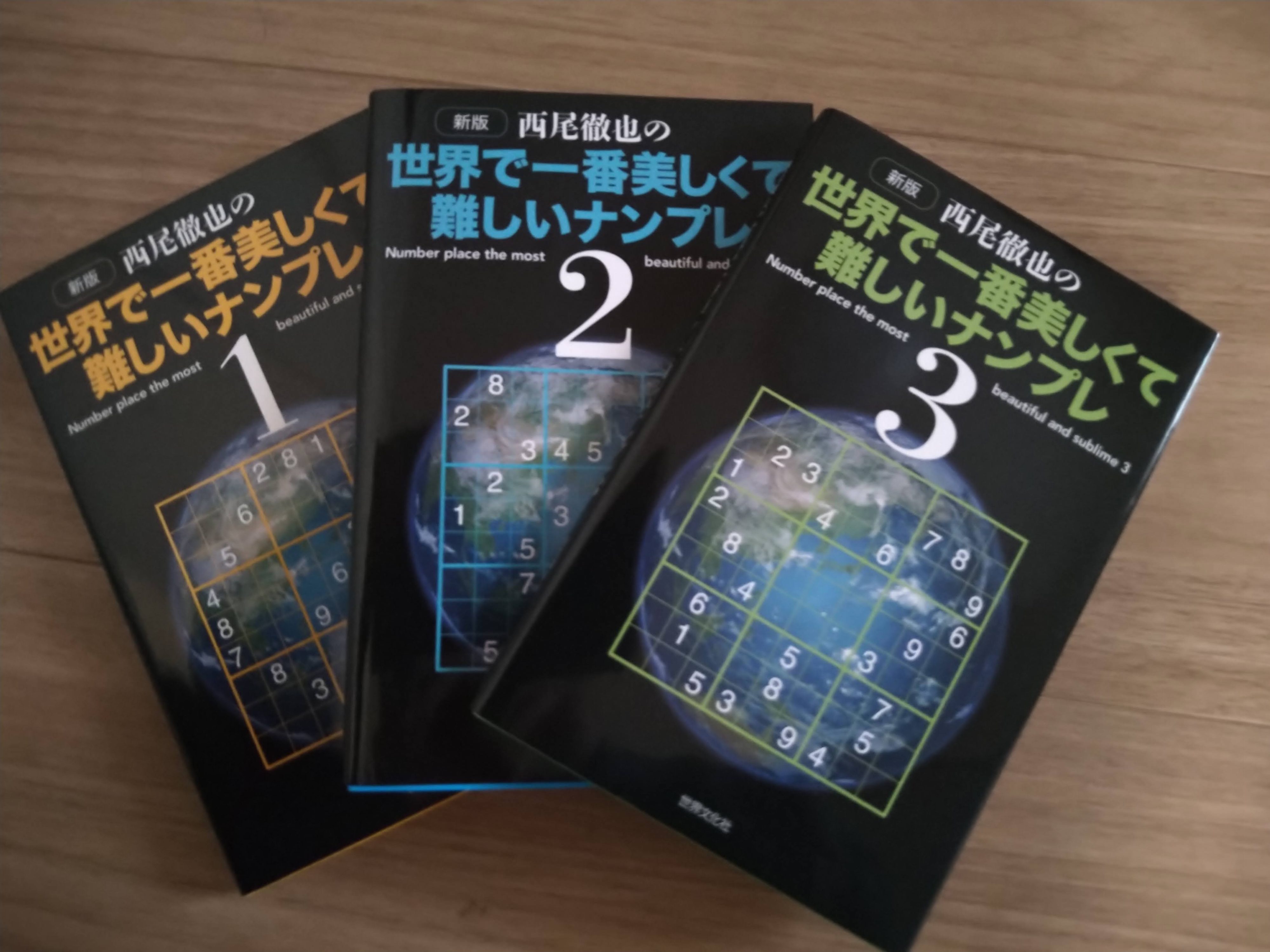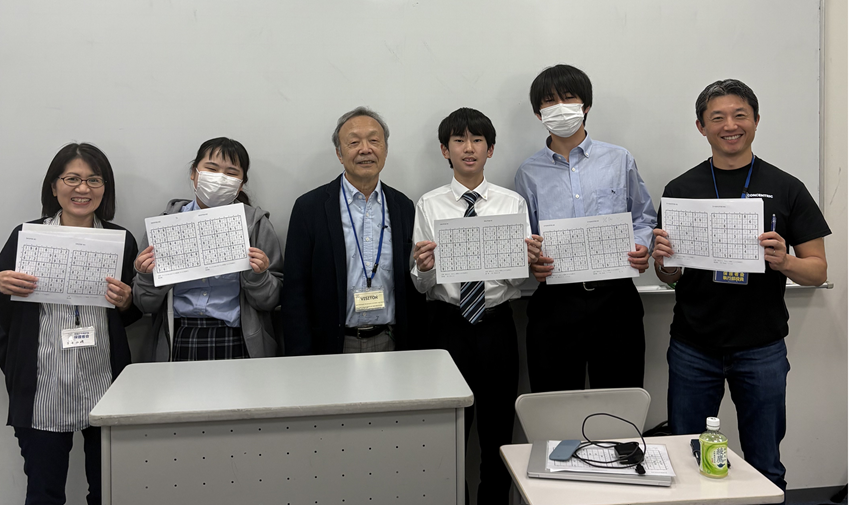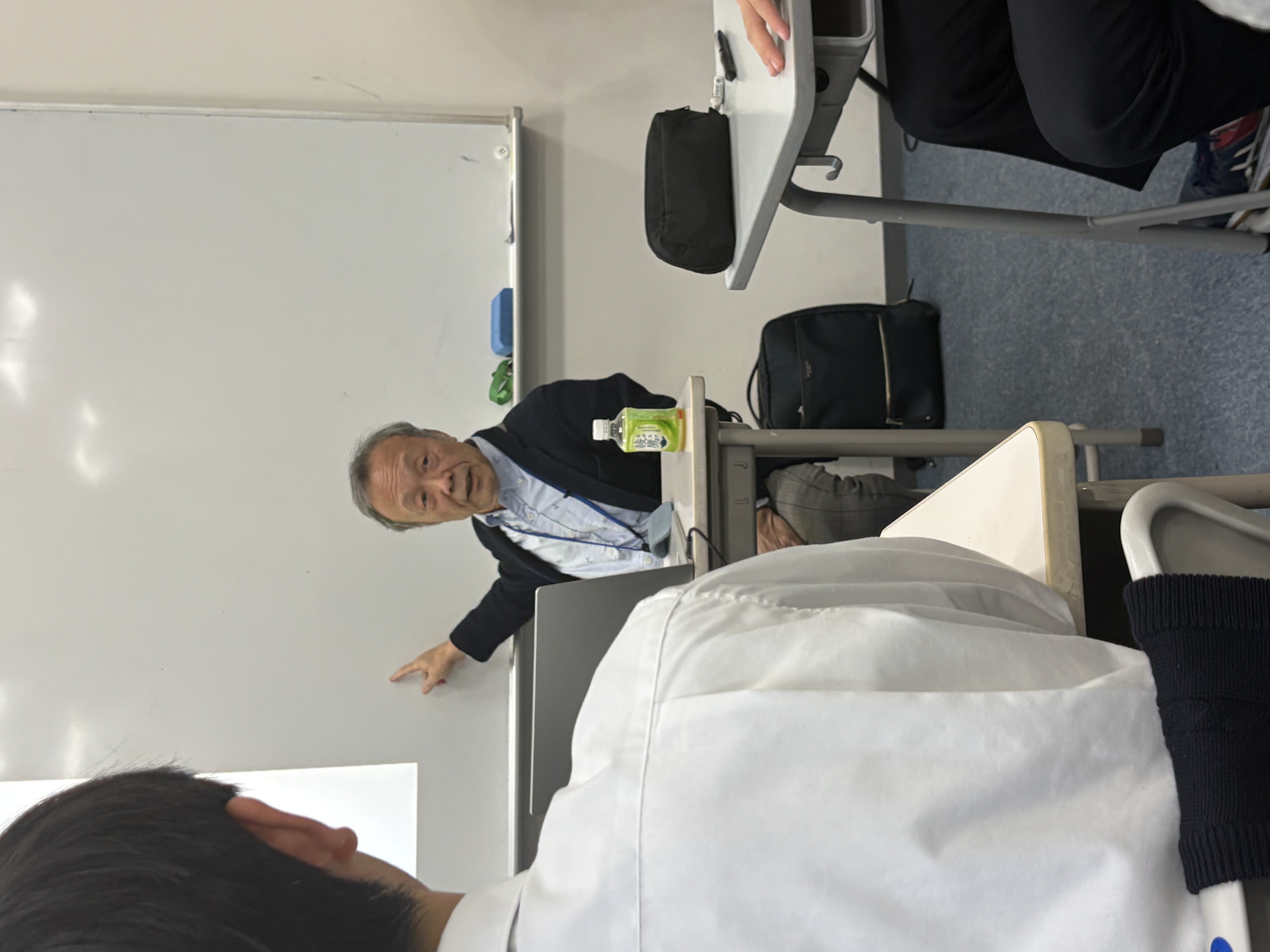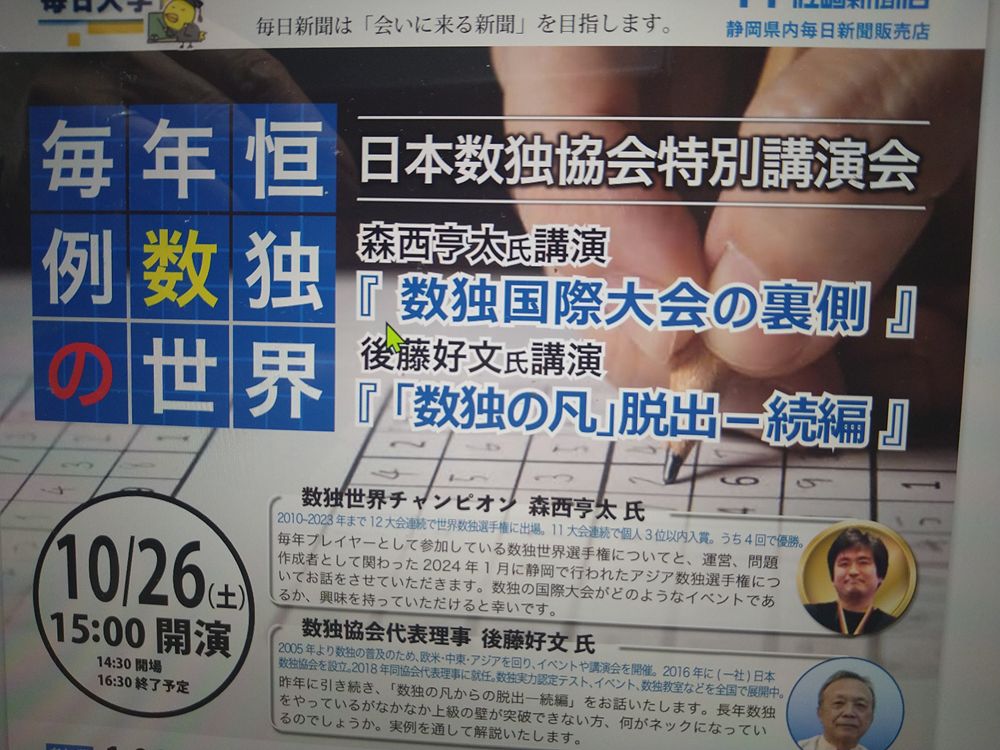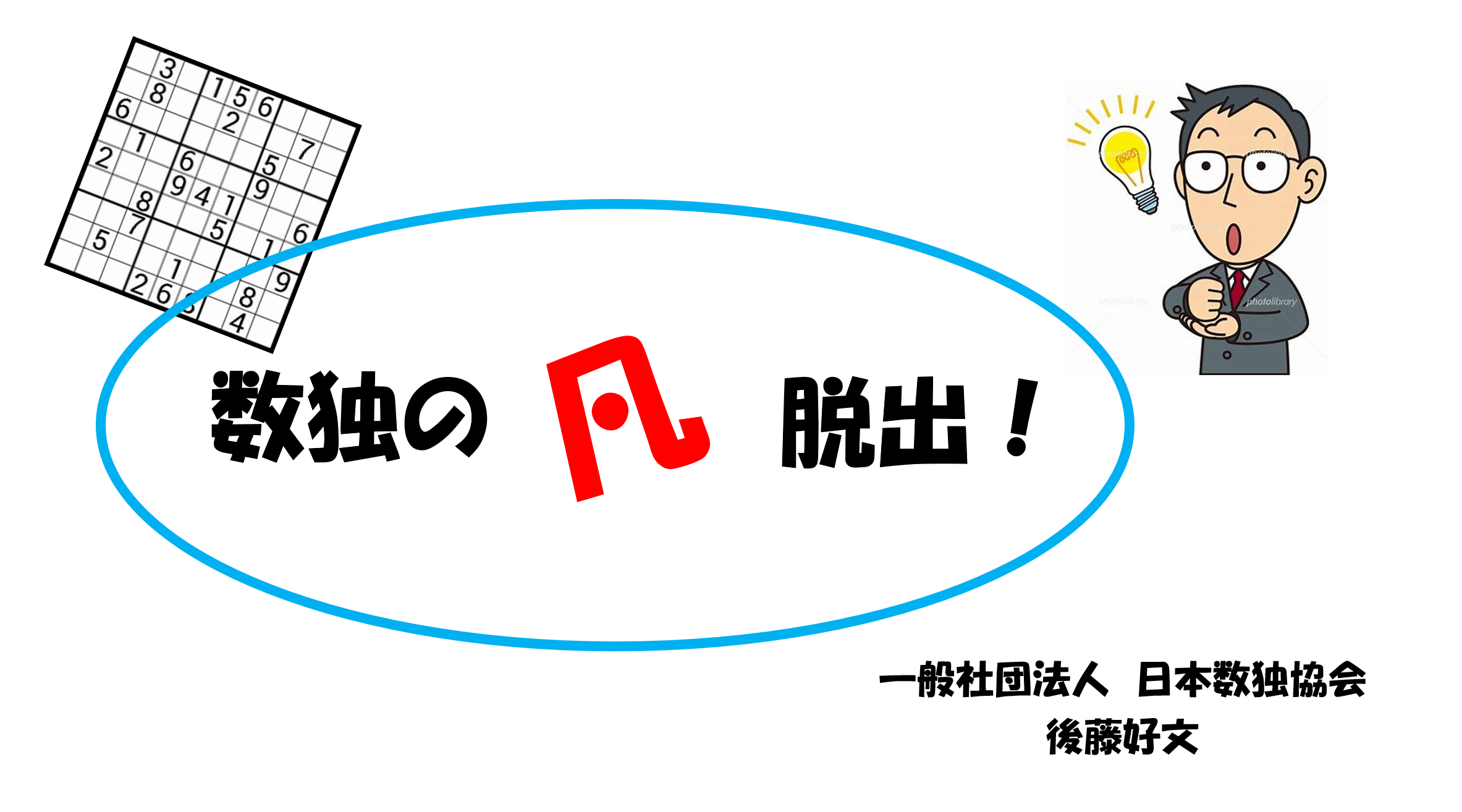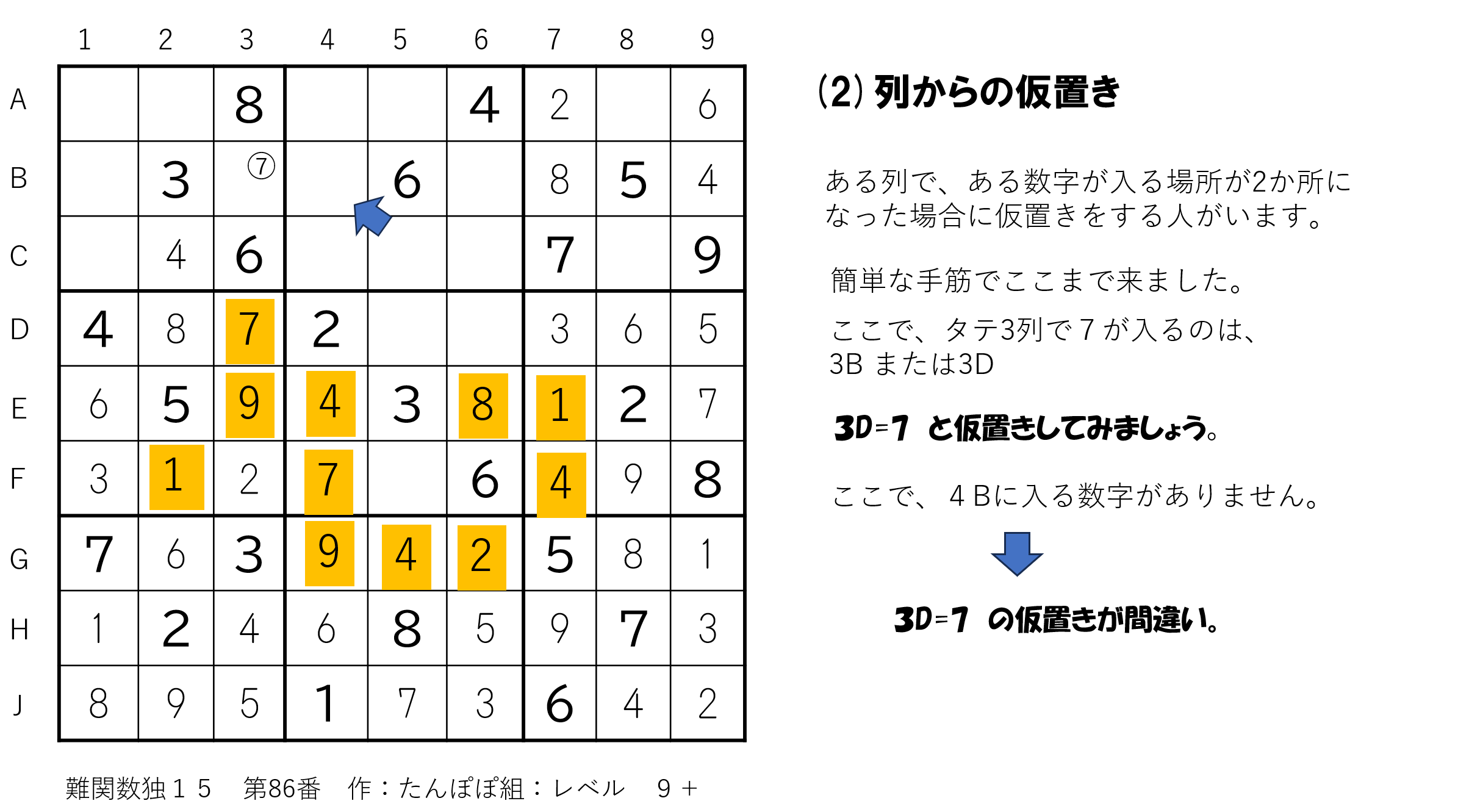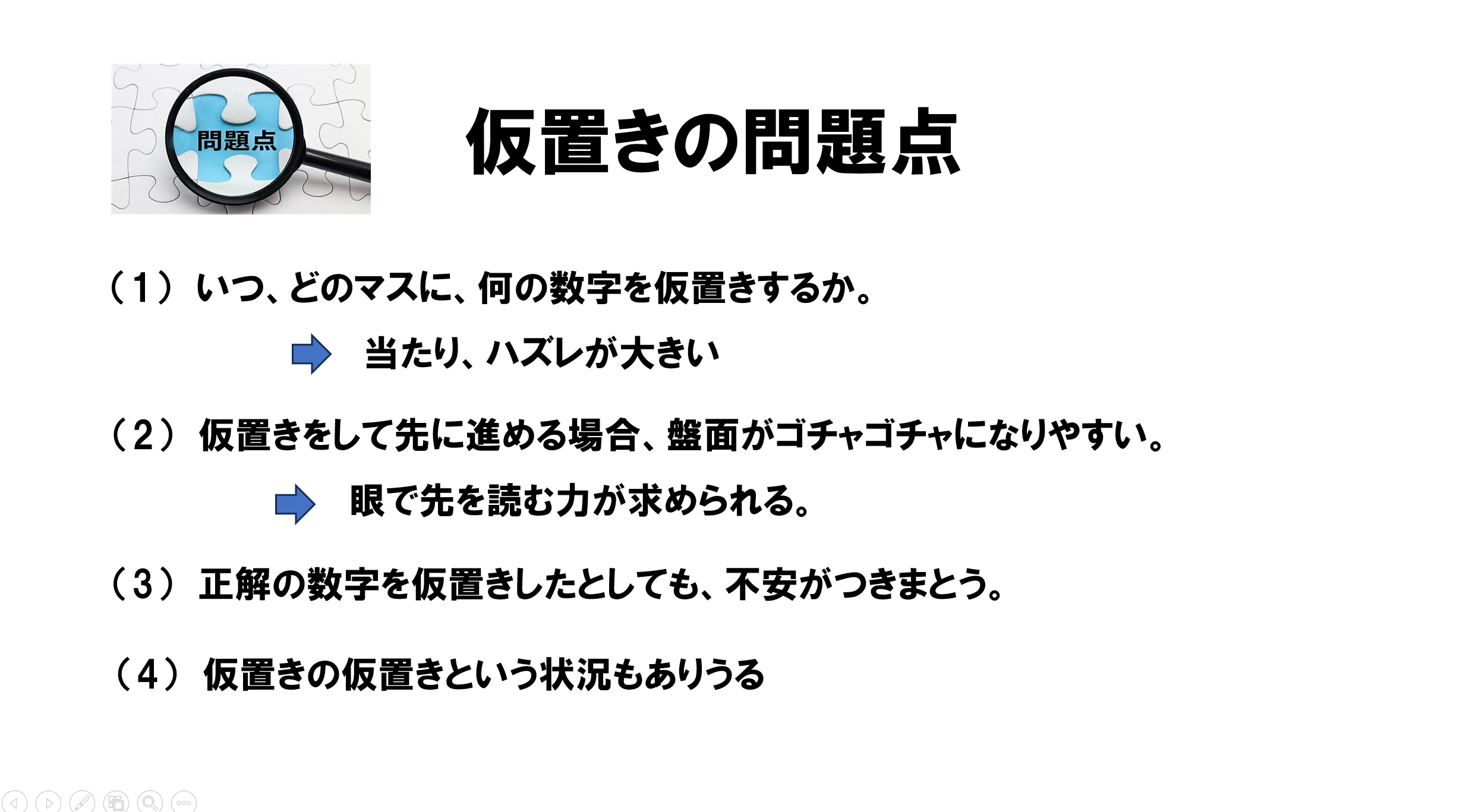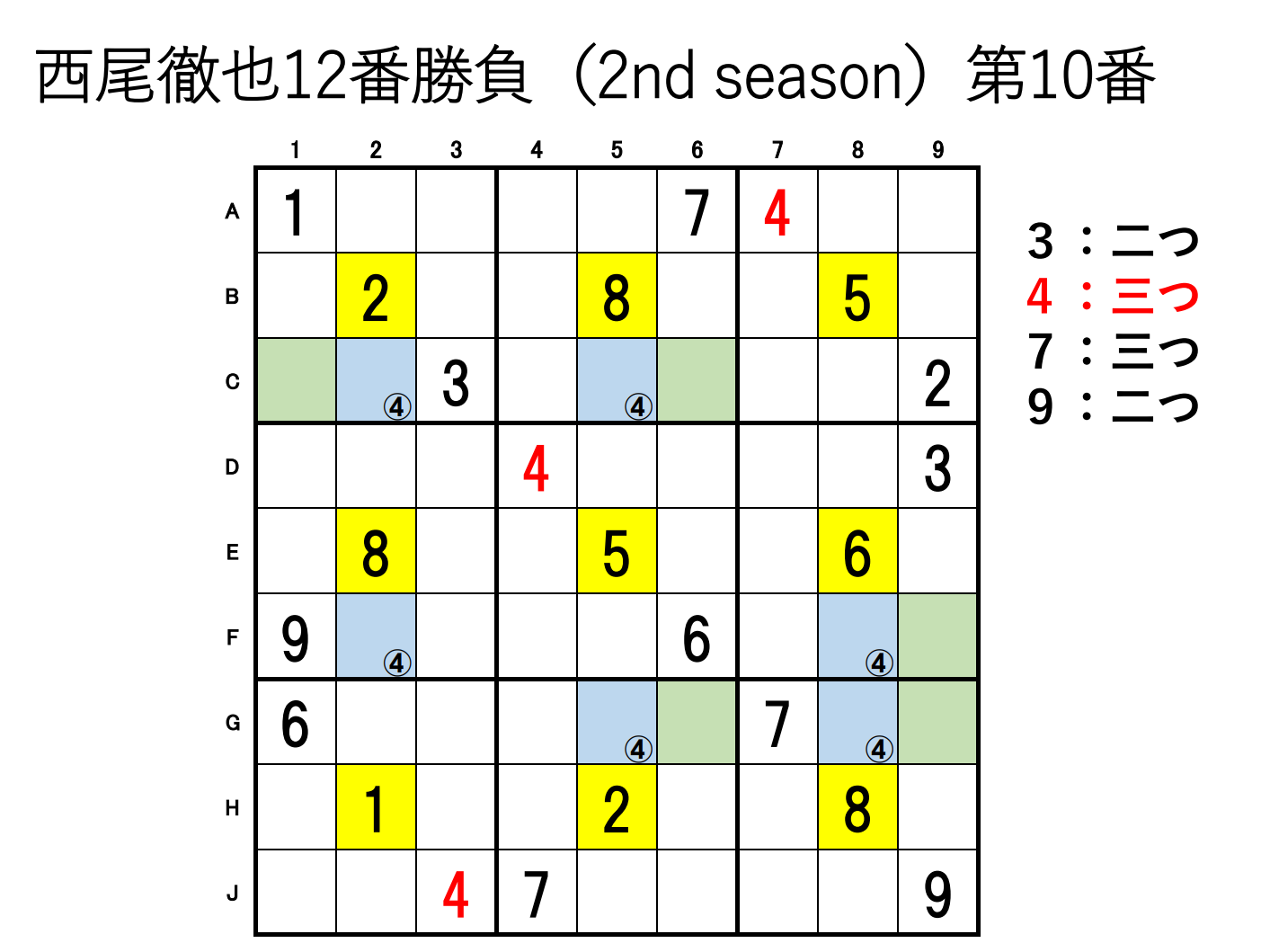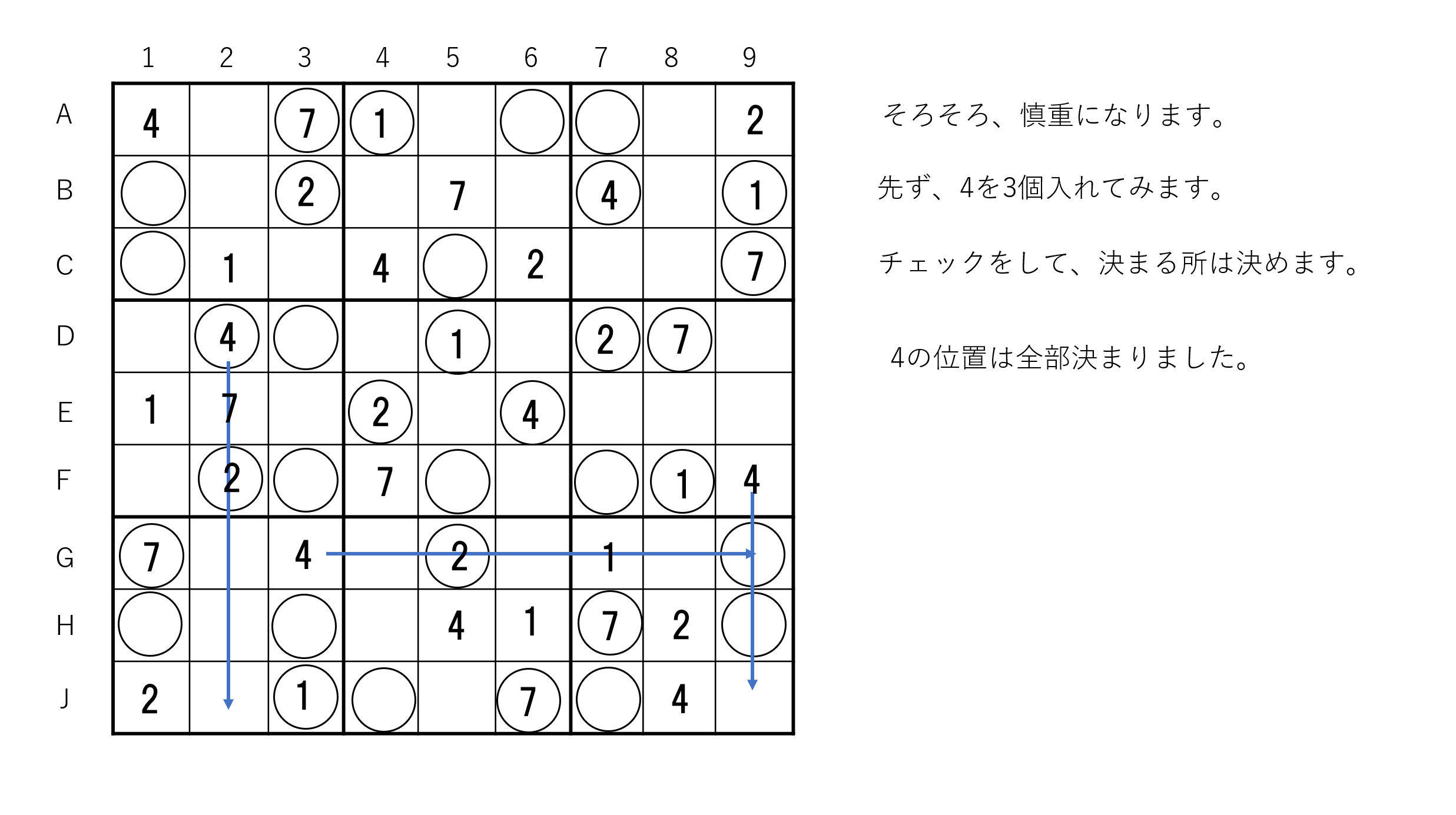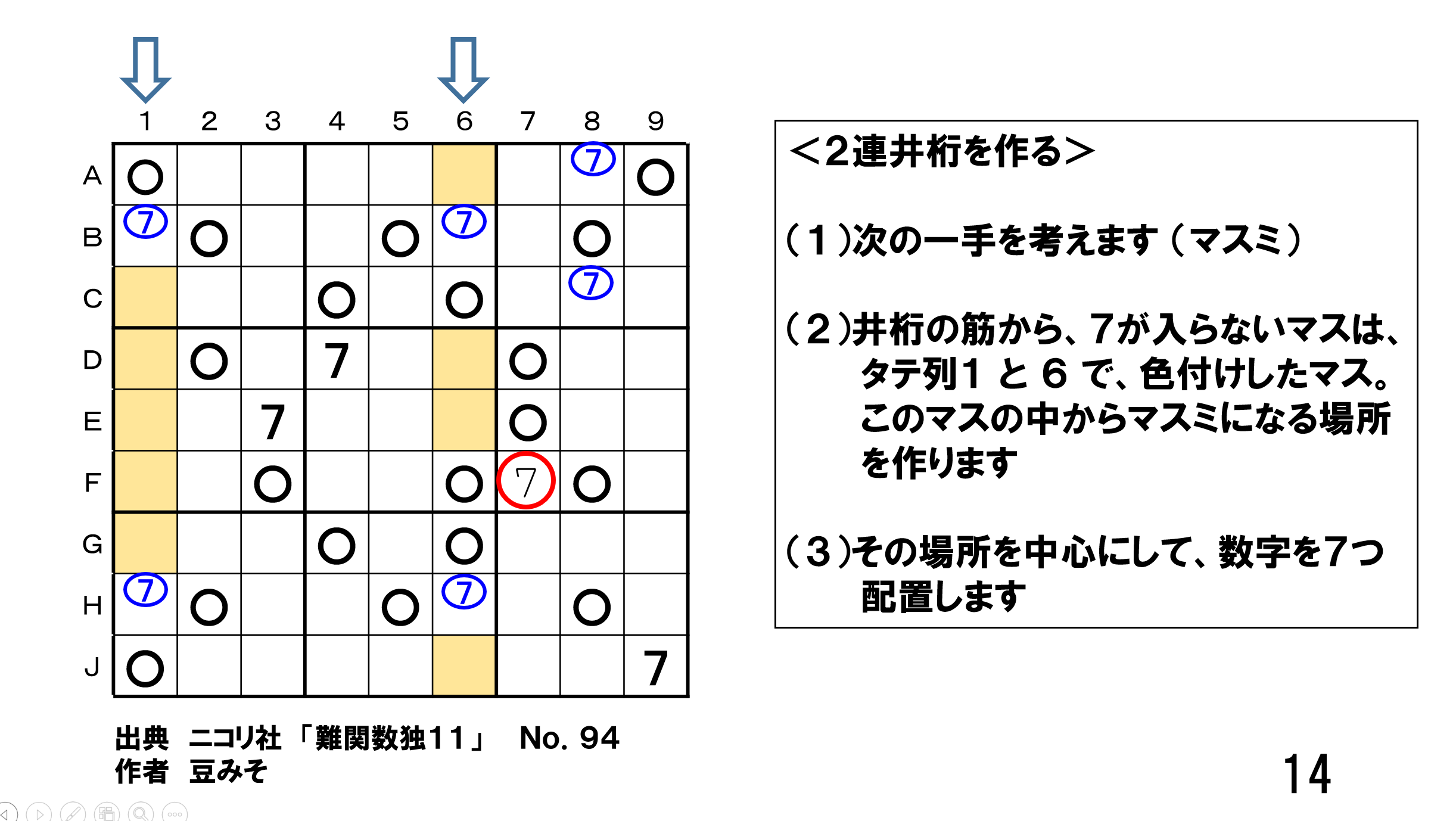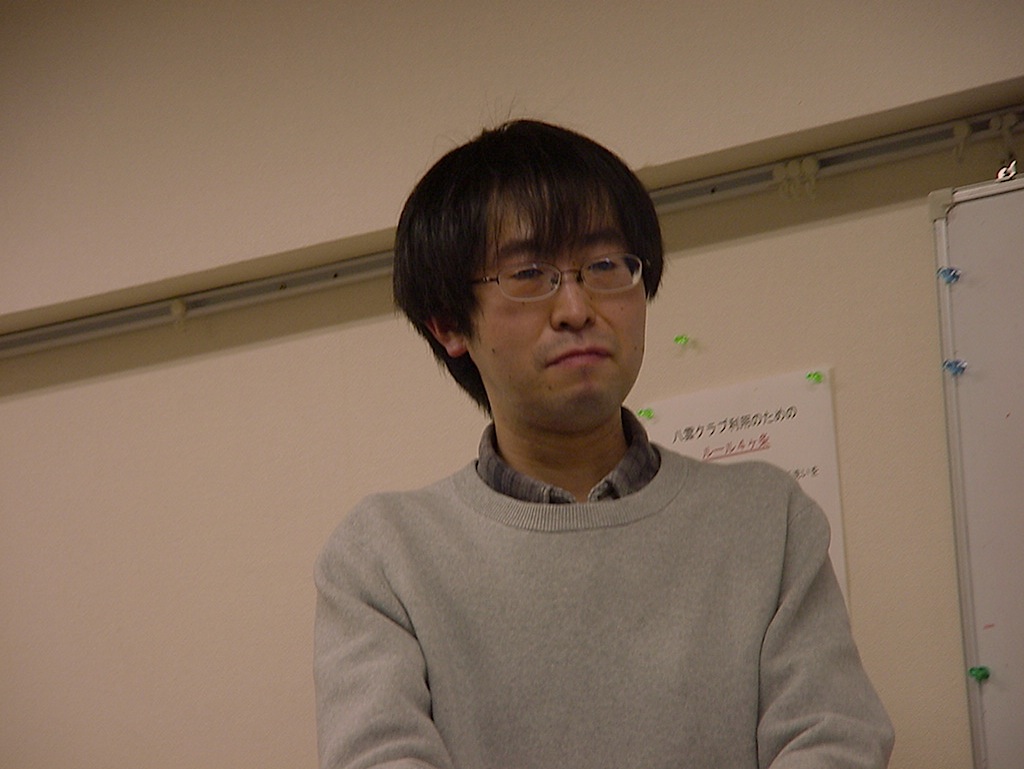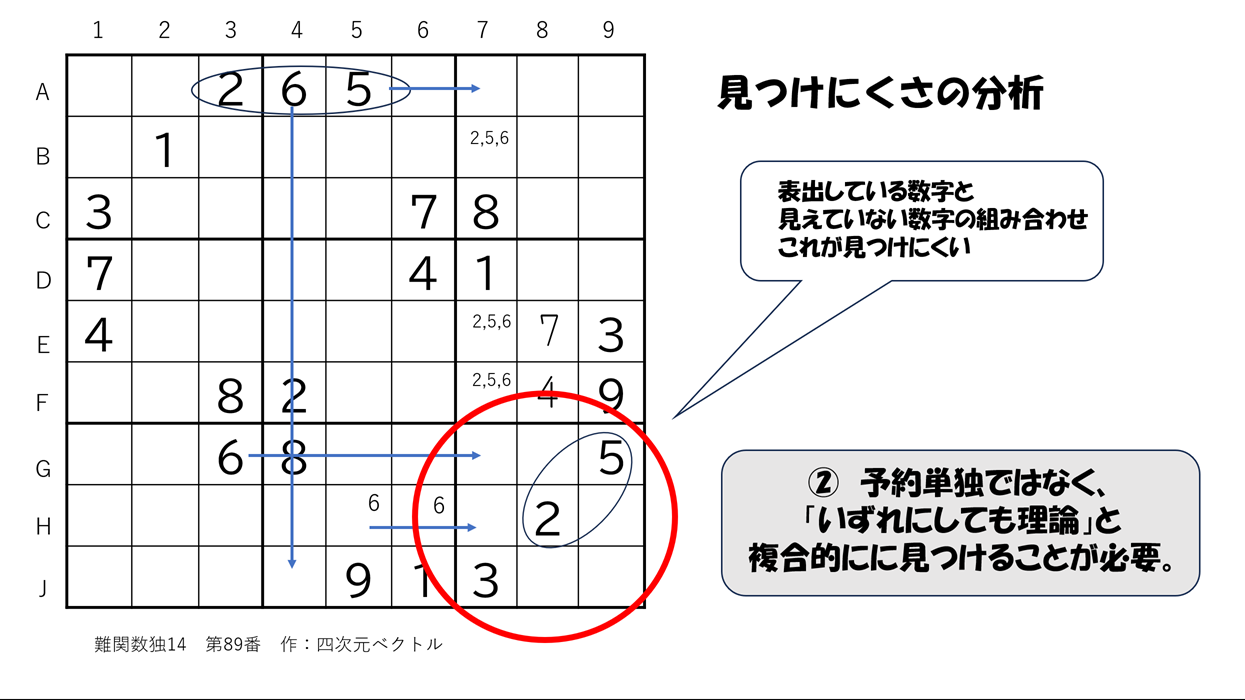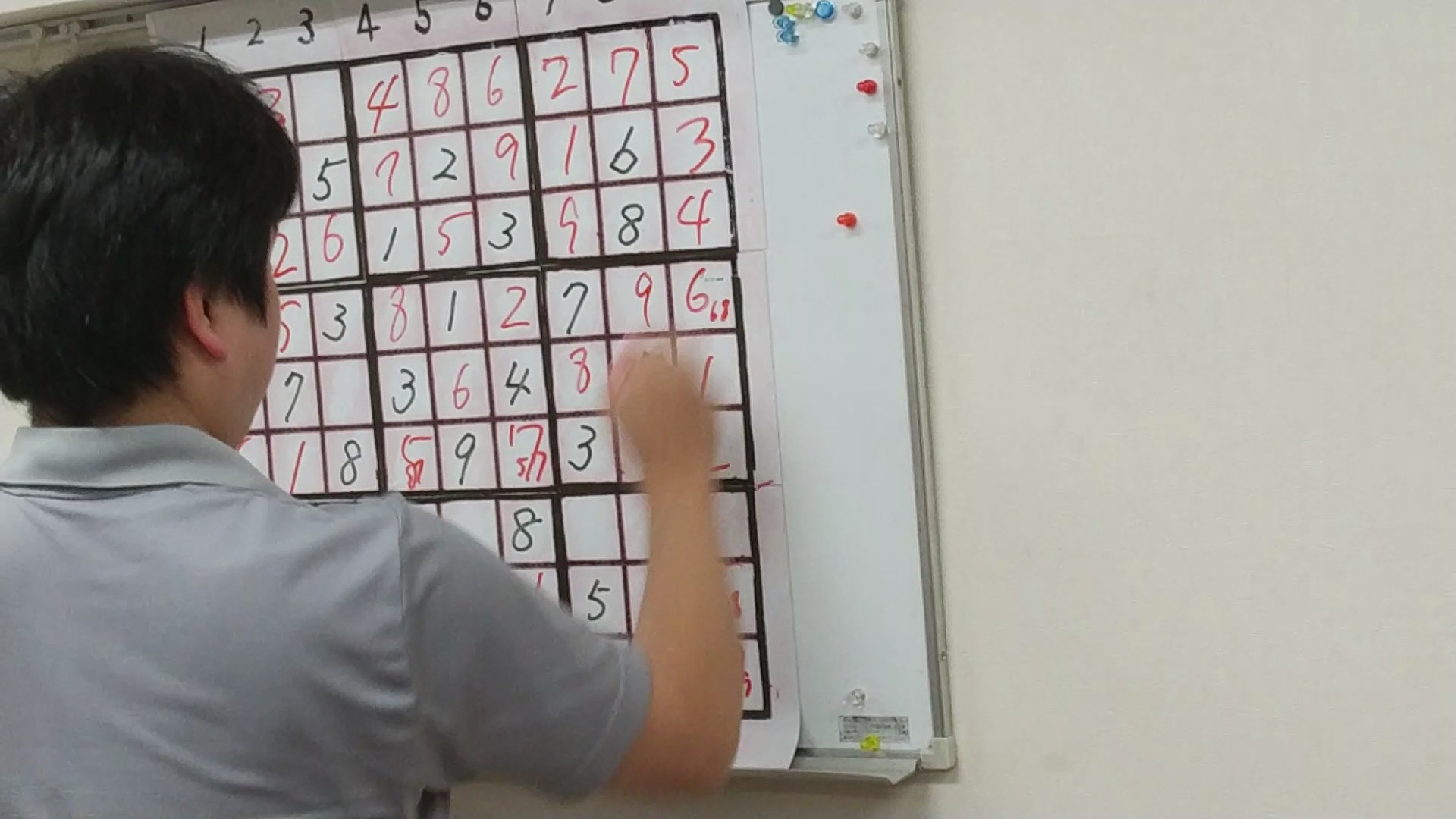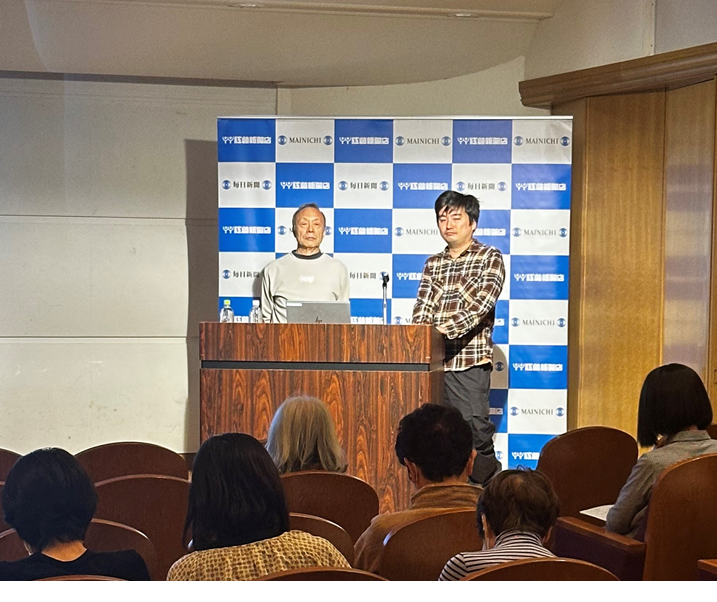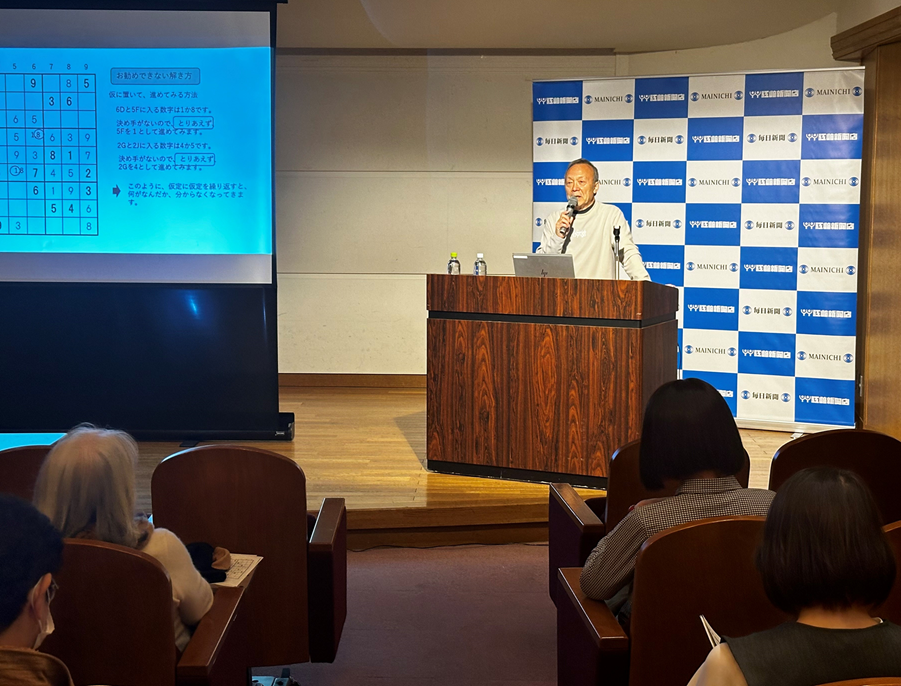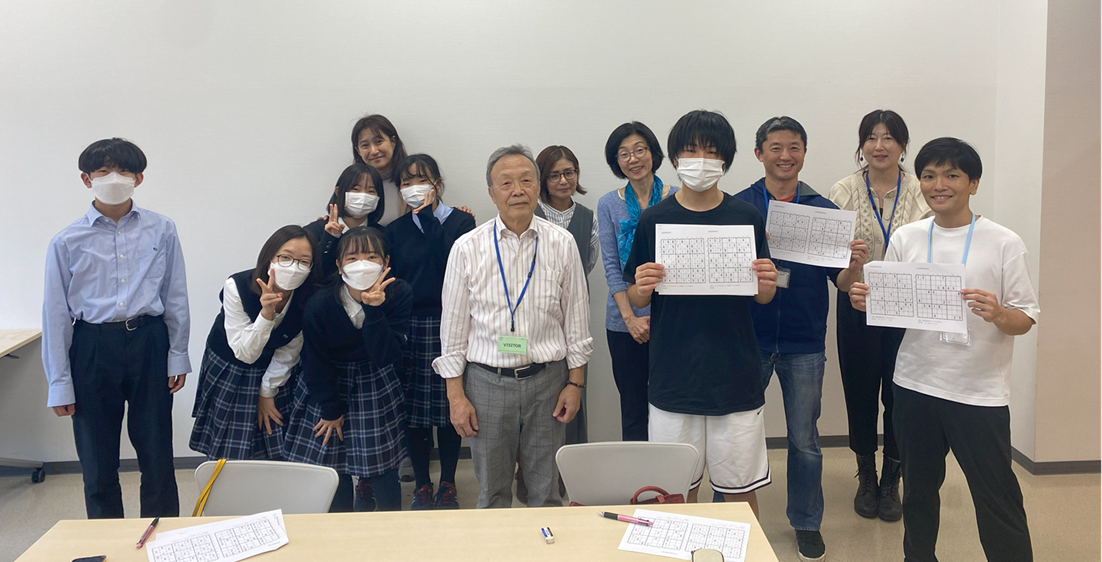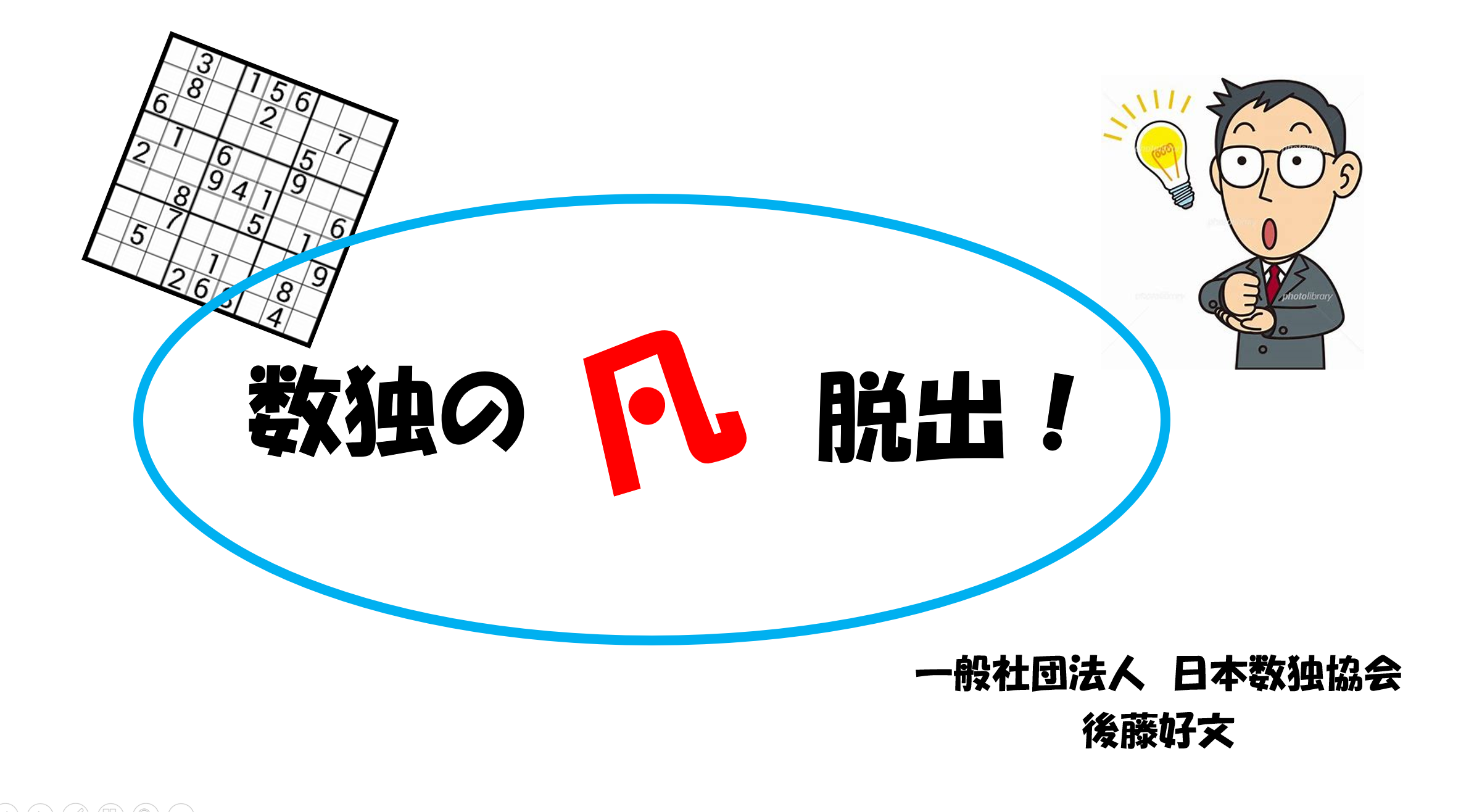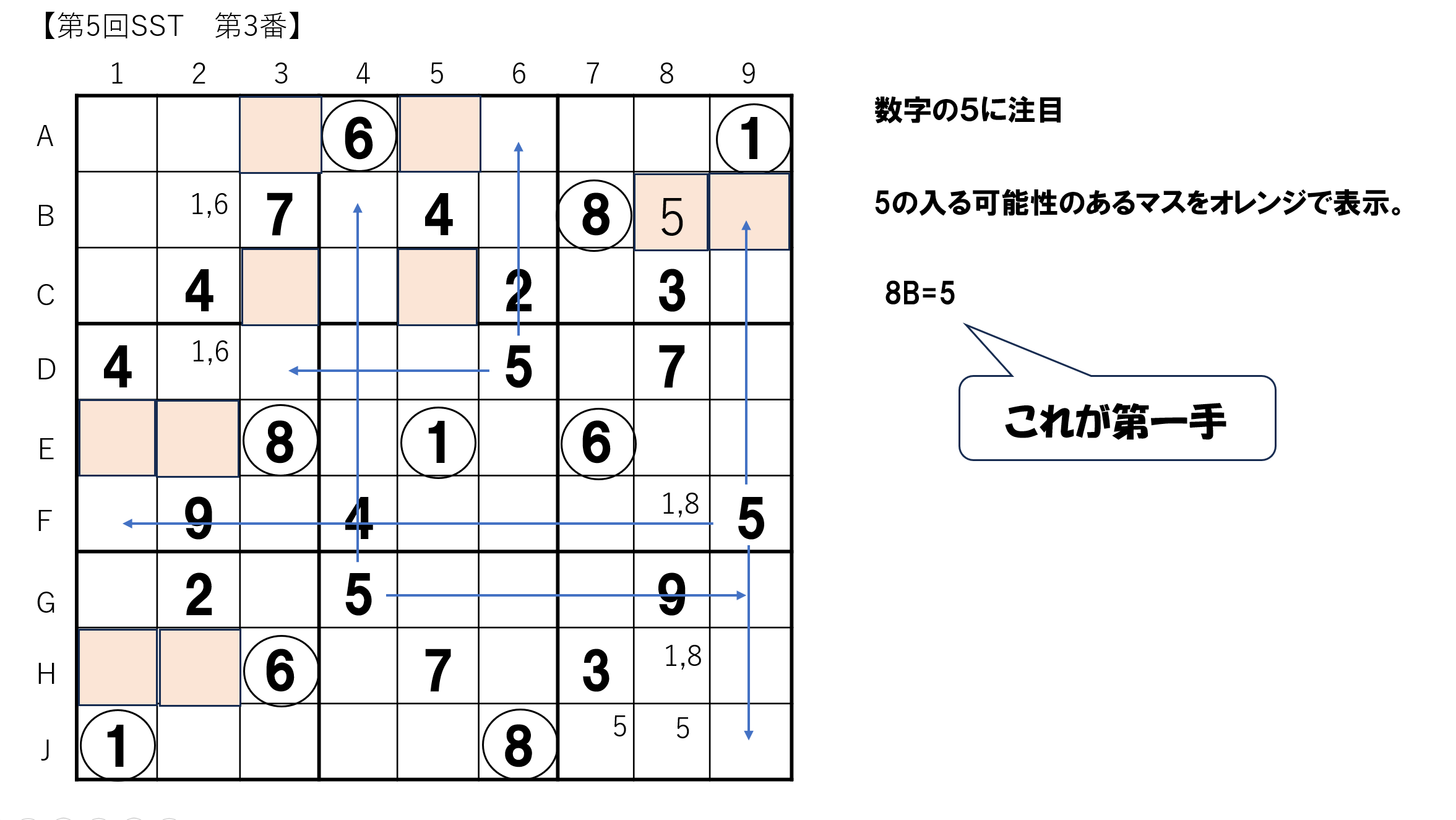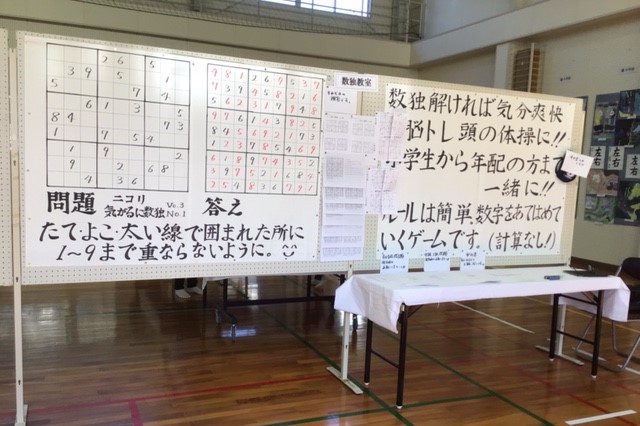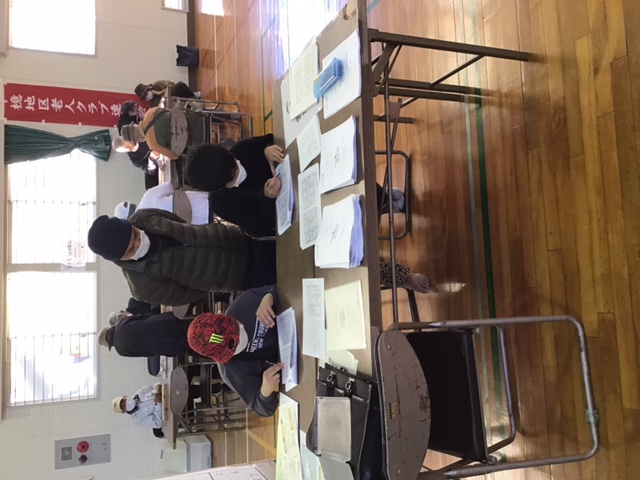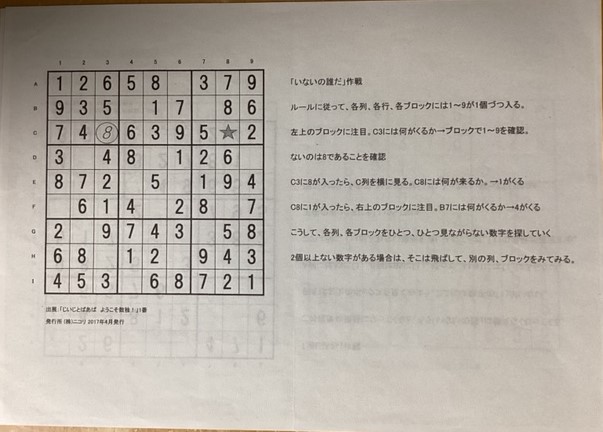ボードによる数独教室
岡山で、「数独ボード」で数独教室を開いている方がいます。
岡山県赤磐市(あかいわし)社会福祉協議会でボランティアをされている桑原五郎さんです。
桑原さんは、ご自身の数独体験から、高齢者の脳トレに何とか数独を取り入れようと
数独ボードを開発されました。
この数独ボードは数字の駒にマグネットが付いているので、取り外しが簡単です。
紙も鉛筆も消しゴムも要りません。
桑原さんは初め数個のボードで、介護施設で数独教室を開いたところ、大変好評で、
次々とリクエストが舞い込んできて、とうとう100台以上のボードを
お一人で制作され、腱鞘炎になってしまいました。
「ボードの利点は、教えやすい、そして理解が早い、何よりもそこからの
コミュニケーションが楽しい。」と桑原さんはおっしゃっています。
介護施設ばかりでなく、小中学校からも放課後や夏休みの過ごし方で、要望が
きており、「一人でやっていくのはもう限界かも」と、思わぬ展開に戸惑って
おられるそうです。